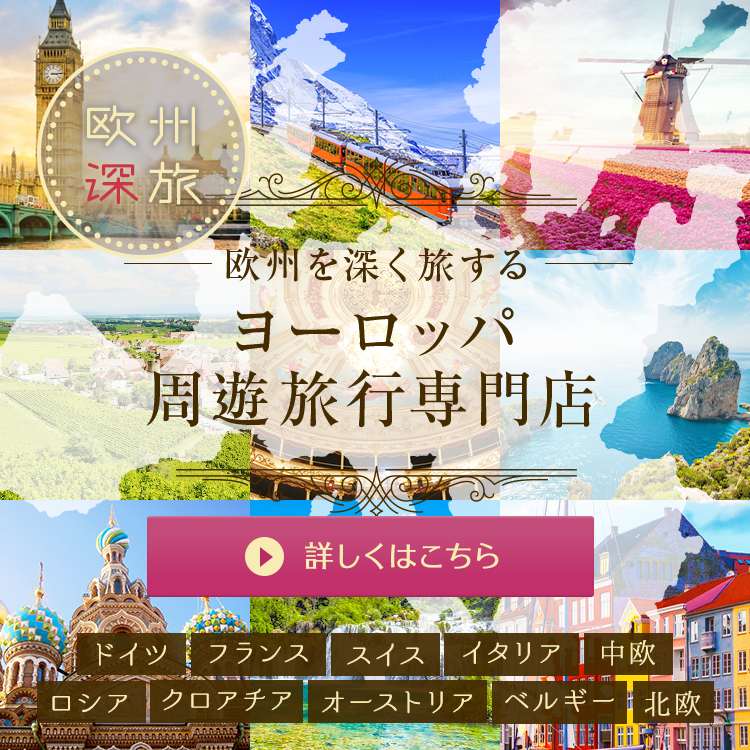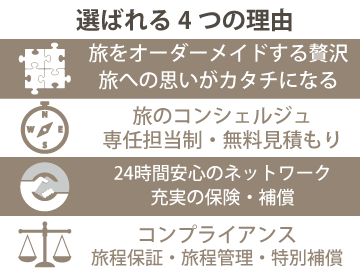そして翌朝、いよいよやって参りましたよ。じゃん!
この礼拝堂が竣工したのは1955年、それからもう半世紀以上の歳月が流れています。
白いコンクリートにも派手に亀裂が入っている部分があるのも目立つし、必ずしも状態が良いばかりではないことも確かで、でも、来てよかった。
礼拝堂の側面。
.jpg)
このあたりはややモダンな意匠を感じさせますが、近代建築の父とも呼ばれるコルビュジエが晩年なって生み出したものは、必ずしも近代の枠組みには収まらないとても自由なものでした。
どこか不揃いでありながら、でも、調和している。そんな感じを愛するのは、それこそがきっと、フランス人のエスプリなのでしょう。
そして、奇妙なのはこの窓の配置。
.jpg)
一見なんでこんな配置になっているのかと感じることと思いますが、これらの位置はもちろん適当に決められたわけではないようなのです。
帰りに礼拝堂のそばにあるお土産売り場で買ったカードに書いてあったのですが、コルビュジエは人間の身体の比率を測り、そしてそれをmodule(単位)とSection d'or(黄金分割)という語をを組み合わせModulor(モデュロール)と呼び、建築の設計に際して利用していたということのようなのです。
このようなどこか有機的な、不思議な印象を与える建物が出来上がったのはそのせいなのでしょうか。
別名chapelle de lumière(光の礼拝堂)とも呼ばれるように、これらの窓を透過して光が差し込んでくる光景は本当にすばらしいかったのですが、建物の内側には神聖な場ですのでカメラによる撮影は御遠慮くださいとの注意書きがあり、今回画像をお見せできないのがとても残念です。
写真集などには内部の写真が載っているものもありますのでぜひ探して見てみてください。
しかし画像よりも何よりも、行って体験することに勝るものはありません。
ぜひ行って御自分の目で確かめてみることをおすすめします。
こんなにも辺鄙な場所にあるのに、毎日、世界中からこの建築を見るためにやって来る人が後を絶ちません。
それだけ人を惹き付ける何かがきっと、この建築にはあるのでしょう。私はそう思います。
追記 現在、ロンシャンの礼拝堂のすぐ近辺ではポンピドゥー・センターや、日本だと銀座にあるエルメスの店舗などを手掛けたことのあるイタリアを代表する建築家、Renzo Piano(レンゾ・ピアノ)の設計による新しい施設が建設されている最中で、 礼拝堂を観覧するのにはとくに支障はないのですが、 完成すると周辺の環境が多少変わる可能性もあり物議を醸しているようです。私が行ったときも礼拝堂の裏手に工事の重機が見えていました。


 ロンシャンへ行く =前編=
ロンシャンへ行く =前編=